ノンアルコールビールは商品によって全然味が違いますし、原材料も大きく異なります。個人的にも「なぜこんなに味が違うのか」「なぜ原材料がこんなにも違うのか」疑問に思ったので今回はノンアルコールビールの製法についてまとめたので解説したいと思います。
そもそもノンアルコールビールとは?
日本の酒税法では、『アルコール分が1%未満の飲料』は酒類とはみなされず、『清涼飲料水』として扱われます。そのため、1%(1度)未満のアルコールを含む飲料は、ノンアルコール飲料というカテゴリーになります。
しかし現在はアルコールが0.00%~0.05%のほとんど含まれないビールのみがノンアルコールビールと呼ばれる場合が多く、1%未満かつ0.05%以上のアルコールを含むビールはローアルコールビール、低アルコールビール、微アルコールビールなど表記されていることが多いです。
ちなみにノンアルコールビールの中で0.00%の商品であれば飲酒運転に該当することはありませんが、ローアルコールビールの場合は、わずかですが確実にアルコールを含んでいるため飲酒運転に該当するので注意が必要です。
| カテゴリー | アルコール濃度 [%] | 商品具体例 |
| ・ノンアルコールビール | 0.00~0.05 | アサヒ ドライゼロ キリン グリーンズフリー サントリー オールフリー |
| ・ローアルコールビール ・微アルコールビール ・低アルコールビール | 0.05~1.00 | アサヒ ビアリー クラウスターラー 正気のサタン |
ノンアルコールビールの製法は大きく3つ
通常のビールの製造方法と発酵について
ますビールの製造方法についてですが、とても簡単に説明すると①原料の仕込み②発酵③熟成のプロセスを経て作られます。アルコールは②の発酵のときにアルコールが生成されるのです。
そのためノンアルコールビールを製造するときには②の発酵の工程で発生するアルコールが邪魔者になってしまうわけです。そのため各メーカーはこの発酵の工程で発生するアルコールをいかに商品に入れないように製造するかがカギを握っています。
以上のことを踏まえて、ノンアルコールビールの製造方法について説明すると大別すると3つに分けられます。
①そもそもアルコールを発酵させない製法(ブレンド方式)
そもそも②発酵をさせないという作り方です。「アルコールが発酵でできてしまうなら、発酵の工程をなくしてしまえ!」という発想ですね。これは麦芽エキスやホップエキス、香料をブレンドしビール風に仕上げる商品はこの方式で作られます。
商品具体例を挙げると「アサヒ ドライゼロ」がこれに該当します。「アサヒ ドライゼロ」では一切麦汁を用いずに、フレーバーなどの調合技術でビールの味を再現するという手法で製造されています。
②発酵を抑えてアルコールを作らない製法(発酵抑制方式)
発酵のプロセスで発生するアルコールをなるべく発生させないようにする手法です。具体的には下記の手法があります。
- 麦汁の糖分を減らす➡糖分の量でアルコールの量が決定するので、糖分の少ない麦汁にする。
- 特殊な酵母を使用する➡酵母の種類の中でアルコールを発生させにくい専用の酵母を選定する
- 発酵の途中停止させる➡発酵途中で酵母を取り除く、発酵中に麦汁を急冷させる。
商品具体例を挙げると「クラウスターラー」や「龍馬1865」が該当します。「クラウスターラー」に関しては意図的に0.5%になるように発酵プロセスを停止させているそうです。
③できたビールからアルコールを抜く製法(脱アルコール方式)
これは通常のビールの作成プロセスを経たのちに、脱アルコール工程を経て製造されるものになります。ビールを製造後にあえてアルコールを抜くためとても手間がかかっています。
商品具体例を挙げると「アサヒ ビアリー」や「アサヒ ゼロ」が該当します。ちなみに「アサヒ ゼロ」脱アルコール方式にも関わらず0.00%です。
製法の特徴(良い点/悪い点)
ブレンド方式の良い点/悪い点
良い点としては完全0.00%が実現できること、大量生産がしやすいためコスト低につながりやすいが挙げられます。
悪い点としては「清涼飲料水」に近い味わいになり、ビール好きには物足りないことがある。人工的な風味になりやすいなどがあります。
確かに「アサヒ ドライゼロ」はビールには独特な後味があることや、特徴的なノンアルコールビール特有のにおいがあることから「清涼飲料水」に近いっていうのは個人的に納得がいきます。
※「アサヒ ドライゼロ」のレビューはこちら
発酵抑制方式の良い点/悪い点
良い点としては製造コストが低いこと、麦の甘みや風味が残りやすいことや、完全0.00%の製造が可能であることが挙げられます。
悪い点としては発酵を途中で抑制するため、甘さが残りやすいことや本格ビールの複雑な香りは出にくいことが挙げられます。
「クラウスターラー」はこれに該当しますが、確かに麦の甘さを強く感じたのアルコール発酵されるはずの糖分が発酵抑制されることで多く残存したからと考えると非常に合点が合います。
※「クラウスターラー」のレビューはこちら
脱アルコール方式の良い点/悪い点
良い点としては本物のビールに近い味わいになりやすいこと、ホップやモルトの香りが豊かなことが挙げられます。
悪い点としては設備投資の観点から、製造コストが高くなりやすいこと、完全0.00%の商品は少ないことが挙げられます。
「アサヒ ゼロ」がこれに該当します。確かに他のノンアルコールビールと比べて本物に近い味わいです。一方で脱アルコール工程が増えるためか、他の商品よりも数十円高くなっているのも納得がいきます。
「アサヒ ゼロ」のレビューはこちら
まとめ
以上の内容を表にまとめると下記のようになります。ノンアルコールビールと一言で言っても大きな差があることが分かりました。ビールの味に近い商品を選びたいなら、③脱アルコール方式の商品を選ぶと良いかもしれません。ノンアルコールビールを購入するときの参考ください。
| ①ブレンド方式 | ②発酵抑制方式 | ③脱アルコール方式 | |
| 良い点 | ・完全0.00%が実現できる ・大量生産がしやすいためコストが低い | ・製造コストが低い ・麦の甘みや風味が残りやすい ・完全0.00%の製造が可能 | ・本物のビールに近い味わいになりやすい ・ホップやモルトの香りが豊かな |
| 悪い点 | ・ビール好きには物足りない ・人工的な風味になりやすい | ・甘さが残りやすい ・本格ビールの複雑な香りは出にくい | ・製造コストが高くなりやすい ・完全0.00%の商品は少ない |
| ノンアルコールビールの商品具体例 | アサヒ ドライゼロ キリン 零ICHI | 龍馬1865 | アサヒ ゼロ ヴェリタスブロイ |
| ローアルコールビールの商品具体例 | ー | クラウスターラー 正気のサタン | アサヒ ビアリー |
参考URL


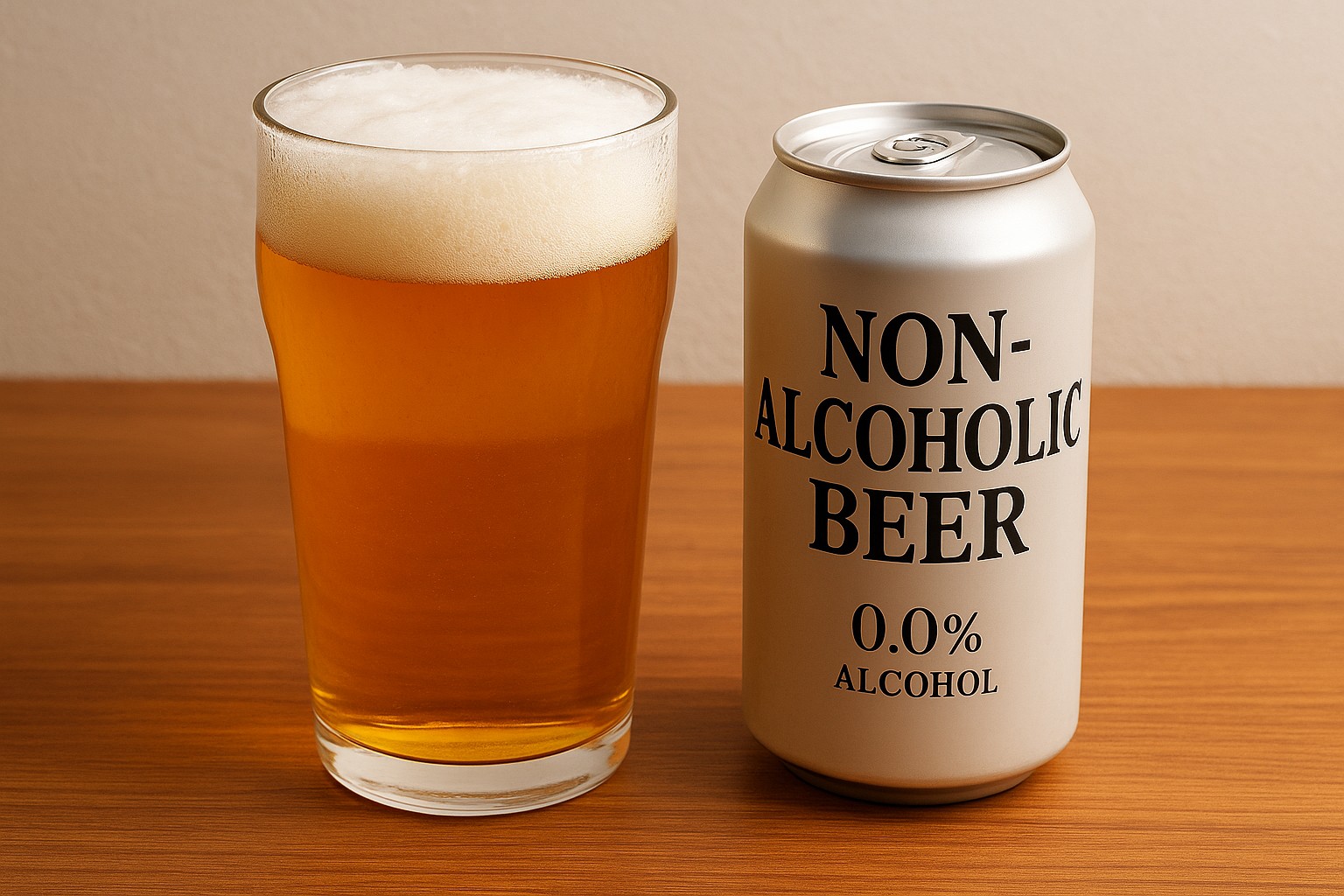
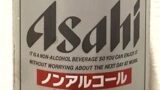




コメント